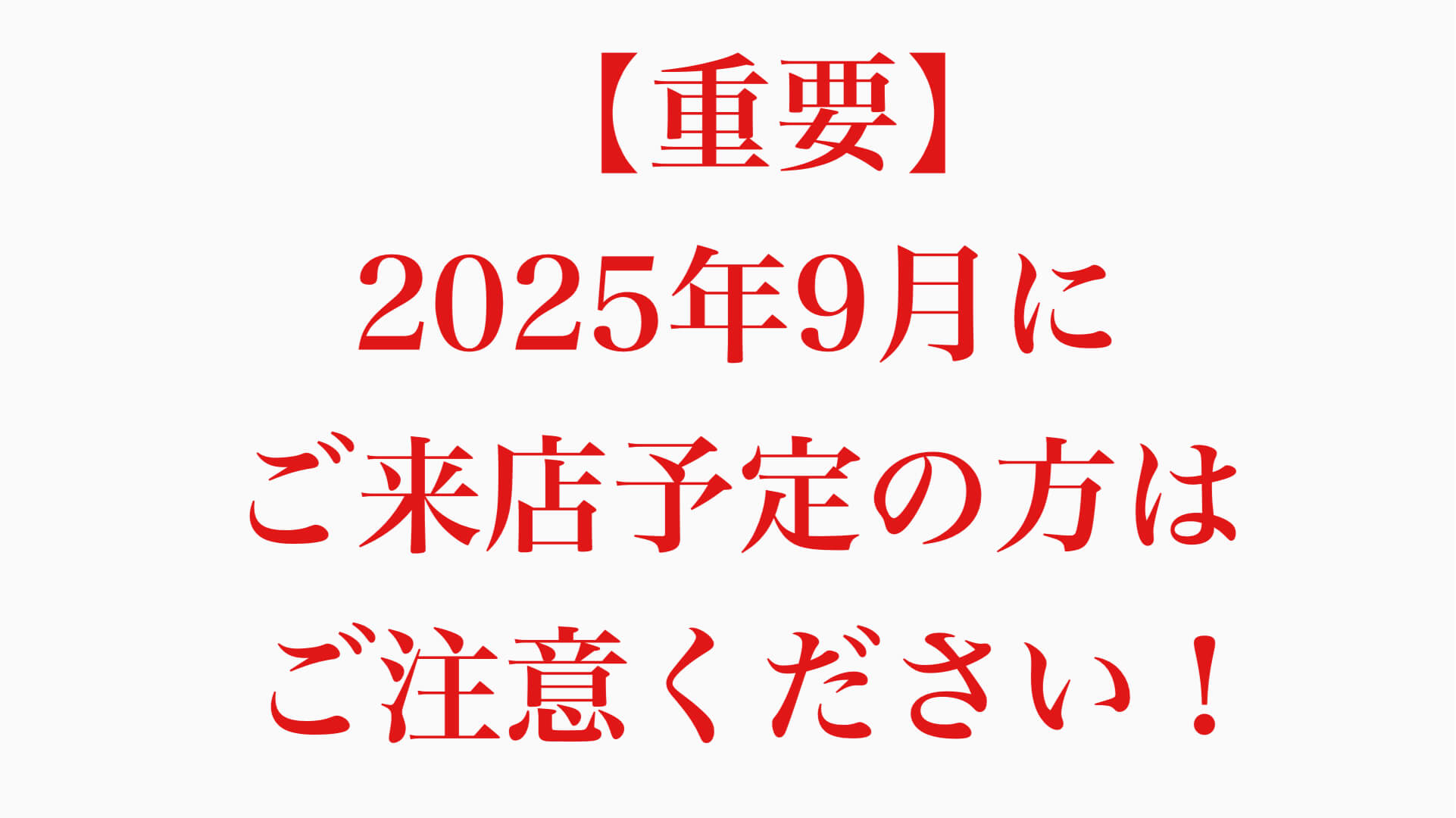「髪質改善」ってどんなもの?そしてアルコに「髪質改善」というメニューがない衝撃的な理由とは?
こんちはー!
福岡市東区の千早、香椎の近く、若宮でボブとショートヘアなどの短いヘアスタイルばっかり切ってる美容師、
「ショート&ボブクリエイター」の岡部ツカサです。
数年前から「髪質改善」って言葉をあちこちで聞くようになりましたが、
実際のところ「髪質改善」ってものは意外と曖昧な言葉だったりして、
美容師さんや美容室それぞれで使い方や定義が違ったり、
お客さんの立場で美容室に行かれる方も、
「髪質改善」のイメージや、「髪質改善」に期待するものって結構マチマチ…(≧∀≦)
そんな「髪質改善」っていう流行りのワードから、
アルコの「意外な事実」についてお話します(○︎´艸`)
「髪質改善」って実はずっと前からあった!?
ここ数年よく聞くようになったワードだから、
「美容業界に新たな革命が起きた!」みたいな雰囲気もあるけど(←そう感じるの僕だけ?笑)
「髪質改善」ってね、ホントのことを書くと、
美容室でしてもらう「トリートメント」(サロントリートメント、システムトリートメントとも呼ぶ)っていうメニューの新しい呼び名( ・∇・)
もっと言うと、
単なる「美容室でしてもらうトリートメントメニュー」を別の言い方をしてるだけ(○︎´艸`)
だから実は「髪質改善」って、ずっと前から多くの美容室のメニューに存在してた、
髪をツヤツヤサラサラにして、それが一定期間持続する「美容室でしてもらうトリートメント」なんです!!
じゃあ、効果も前のと同じ?
「髪質改善」だけでなく、
過去にも「生トリートメント」「水素トリートメント」なんて次々新しいトリートメントが出ていましたが、
どれも実は根本的にはやってることは一緒ですし、
結果的にどれもツヤツヤサラサラになってそれが一定期間続きます。
まあもちろん美容室でしてもらうトリートメントで使う物の成分的なものはいろいろ変化をしていますが、
髪に何かしらの成分を浸透させる(内部に入れる)→表面をしっかりコーティングして手触りをよくする
この構図は変わってないんですよね〜( ̄∀ ̄)
それを証拠に、過去のいろんなトリートメントであっても、髪質改善であっても、

美容師さん)「仕上がりサラサラですよ〜」
お客さん)「ホントだー!サラサラ♪」
…っていう最終的なこのやりとりは変わってないしおんなじだからね…笑笑
(おまけに仕上がりの写真の、このツヤツヤ感も昔から変わってない笑)
…ということを踏まえて、
「髪質改善」や過去のなんちゃらトリートメントを総まとめして「サロントリートメント」として話を進めていきます。
アルコには「サロントリートメント」というメニューはありません!!
「こんなに髪質改善って流行ってるのに…無いの??」
な〜んて声も聞こえてきそうですが笑
髪質改善ってものも無ければ、過去のいろんなサロントリートメントもしてないしで、
福岡市東区の美容室「ヘアープレイスアルコ」には、後にも先にも「サロントリートメント」っていうメニューがないんです。
おそらく、福岡市東区のではウチぐらいじゃなかろうか…(*≧︎∀︎≦︎)∩︎〃ウヒャヒャ!!!!!
髪の傷みへの対策は「サロントリートメント」だけじゃない!
サロントリートメントというメニューがない、サロントリートメントをお客さんにしないと聞くと、
「え?じゃあ髪のダメージとかはどうでもいいってこと?」
なんて思った人もきっといらっしゃると思いますが…(実際、以前お客さんからそう言われたこともあります笑)
もちろんそんなことはありません(。-∀︎-)ニヒ♪︎
僕だって、お客さんの髪に必要以上にダメージを与えたくないし、
ガサガサに傷んで見えるよりはサラサラでツヤツヤに見えたほうがいいと思ってるし、
サロントリートメントというメニューがあることを否定してる訳ではないんです。
ですが、
ツヤツヤサラサラに見せたり、ダメージを最小限に抑える方法が「サロントリートメント」だけではなく、その他にも方法があるんです!
お客さんの髪をキレイにする(キレイに見せる)気持ちや目指すところは一緒なんですが、
その「方法」が違うってだけなんです(*^^*)
キレイに見せることを「毎日する」っていう方法。
サロントリートメントの特徴は、傷んだ部分がサラサラツヤツヤ になって、それが一定期間「持続する」ってところ。
だから2〜3週間に一度、美容室に行ってお金と時間を使ってサロントリートメントをして貰えば、
毎日はお家で特別何もしなくてもサラサラツヤツヤになるわけで、それが良いと思うかもしれませんが…(実際はデメリットもあるけど…)
対して僕の考えとしては、
毎日ツヤツヤサラサラな状態でいるために、
ツヤツヤサラサラにすることを毎日お家でしてもいいんじゃないか?ということです。
一定期間持続するんじゃなく、その日一日キレイに見せたりツヤツヤサラサラにすることを、
毎日続ければずっと髪キレイじゃん!って思うんです(*≧︎∀︎≦︎)
これは顔でいう「メイク」と同じで、
毎日メイクをされる特に女性の方は、毎朝メイクして毎晩メイクを落としてを毎日繰り返して、いつも素敵な自分でいられてますよね?
それが僕が考える「キレイな髪でいる方法」であって、
その考えで「サロントリートメント」を考えると、
「一定期間落ちないメイク」をお店でしてもらって、崩れて始めたらまたそれをお店でしてもらっても「素敵を持続」させるって事で、
「顔」で例えるとどちらが良いか?ってのはすぐに答えが出てきそうですが(≧∀≦)
…って事で、僕が考える「髪をキレイにする(見せる)方法」っていうのは、
ちゃんとした物でや方法で、キレイにする(見せる)ことを「毎日する」
という意外とシンプルなんです(○︎´艸`)
※具体的な方法や物については次回の記事で。
毛先のダメージは「最小限」に。
さっきも書いたけど、髪の毛に与えてしまったダメージっっていうのは、
サロントリートメントやなにかをしたら「治る」というものではなく、(傷んでないように取り繕うことができるけど)
切らない限りはずっとダメージを受けたまま。
ダメージを与え続ければ、サロントリートメントや毎日のお家でのケアでキレイに見せることも難しくなるし、
パーマやカラーの仕上がりもうまく行かなくなってくるし、
「傷みの限界」を超えたら、チリチリ、ビリビリって感じになって「髪が崩壊」してしまうこともあって、そうなったらホントに切るしかなくなります。
サロントリートメントで髪のダメージを治すことができるなら、僕も迷わずサロントリートメントというメニューを作るけど(≧∀≦)
今のところはそんなことも本当にないのでサロントリートメントというメニューはそこまで必要ないかと思いますし、
ツヤツヤサラサラに「キレイに見せる」こと以上に、
なるべく「ダメージを最小限にする」ということも大事なヘアケアなんですよね。
サロントリートメントじゃなく、○○○で毛先のダメージはリセットしてる!?
これは今のアルコの特徴からのお話になるんですが…
アルコはゲストの9割以上が「ボブ」「ショート」などの短いヘアスタイルの美容室です。
だから9割以上のお客さんが、パーマやカラー等のダメージ、お家でも扱いや日々生活する上で受けるダメージで、毛先が傷みすぎ扱いにくくなる前に、
毛先を切っちゃう(≧∀≦)
だから、サロントリートメントでツヤツヤサラサラにしてそれを一定期間持続させないと、どうにもこうにもならないって状態までなることがほぼないんです笑
(もちろん、ブリーチや縮毛矯正などの特殊メニューをめちゃくちゃに繰り返すとショートでもかなり傷みます)
これは「短いヘアスタイル」のメリットの1つなんです。
髪の毛っていうのは毛根から生えてきてから、
髪を洗ったり乾かしたり、アイロンで巻いたり寝てる時の枕と頭の摩擦、ヘアオイルやスタイリング剤を付けるなど…生活する上での「ダメージ」や、
パーマやカラーと、時にカットなど、美容室での「ダメージ」を受けながら伸びてくるわけで、
髪の毛が長ければ長いほど、毛先ってのはそんなダメージを受ける回数が多くなり、傷み具合も激しくなってきます。
逆に短ければ短いほど、毛先の受けてるダメージってのは長い髪の毛先に比べて少なくなるってことです(^ ^)
サロントリートメントやお家で使うヘアケア商品で、傷んでる部分をキレイに見せることはできますが、素の「傷んでない状態」に治すことはできないので、
切らない限りは毛先のダメージはずっと残ったままなんです。
だからある意味「カット」っていうのは「毛先の最強の治療法」なわけです!(長さ変わっちゃうけど笑笑)
今回の記事のまとめ。
「まとめ」っていうか、一旦締めるために強制的にまとめます…笑笑
アルコに「サロントリートメント」がないのは、僕の考え方や髪の傷みへの対策や、アルコの特徴やきてるお客さんなど…
いろいろな目線で見て、
「なくても特別困ってないから」です(≧∀≦)
だからもしかしたら今後必要な時が来るかもしれないし、
ごく稀に「サロントリートメントで一定期間ツヤツヤサラサラに見せる方がいいのかな?」って思う時もあるんですが、
それをすることの「デメリット」もあるわけで、だったら今のところは無くていいかな〜って感じなんです。
ですが、
サロントリートメントをされてる美容師さんや美容室のように、
「お客さんの髪、お客さん自身をキレイにしたい」
という気持ちは一緒です!
※次回は、アルコがオススメしてる「毎日キレイな髪でいるため」のお話をしていきます。(予定)
【関連記事】
【髪質改善をしてもらう前に読んで欲しい!】その前に「改善」すべきこと。
「髪質改善」「酸熱トリートメント」に興味ないって言ったら笑われた(笑)
これがホントの「髪質改善」?傷んでる髪をキレイにする、とっておきの方法。
※過去の記事と今回の記事で多少表現が違う部分もありますが、ご了承ください。
⭐︎アルコでの施術の様子、
お客さんの素敵なヘアスタイルを動画で♪
YouTubeチャンネル[アルコのツカサさん]
絶賛配信中!
↓チャンネル登録よろしくお願いします↓